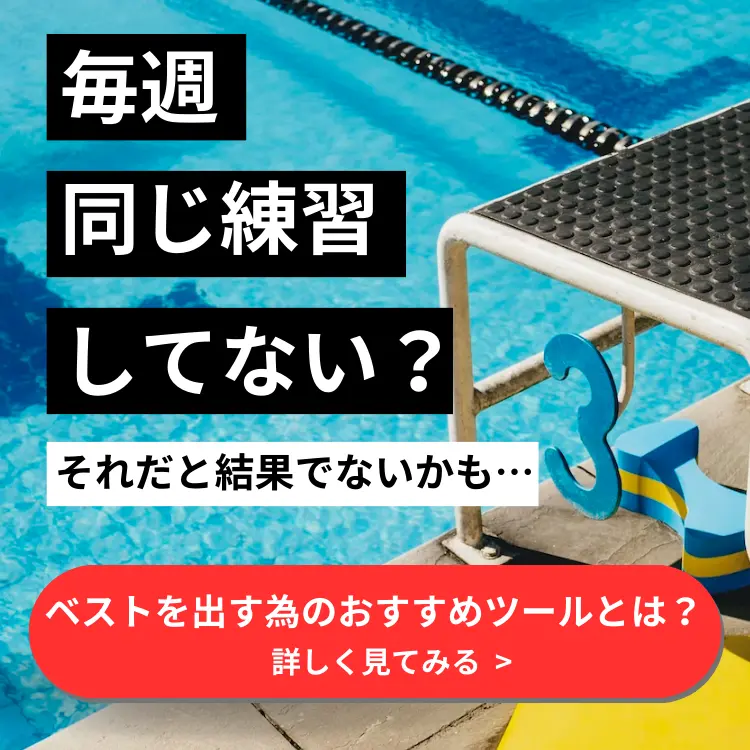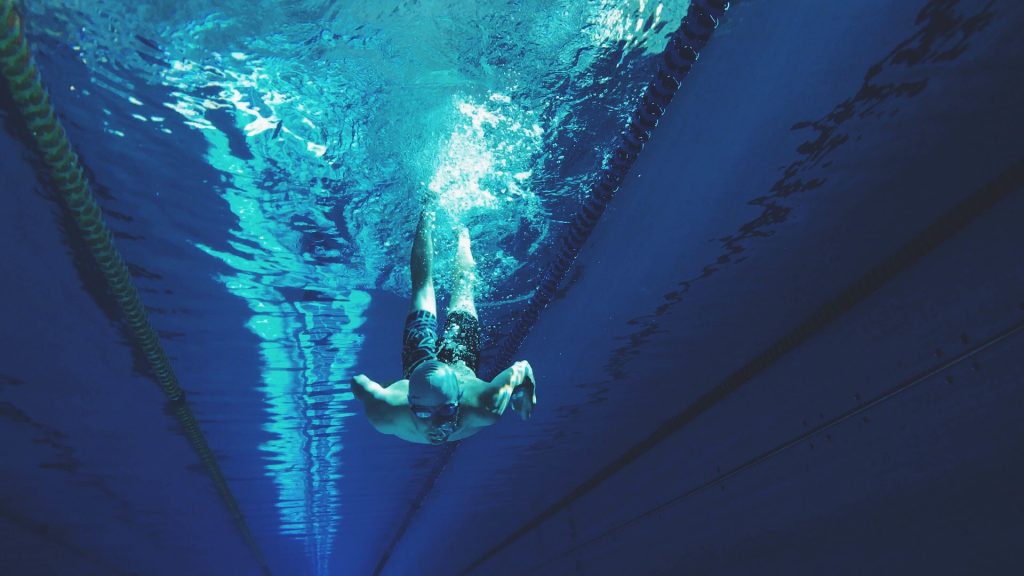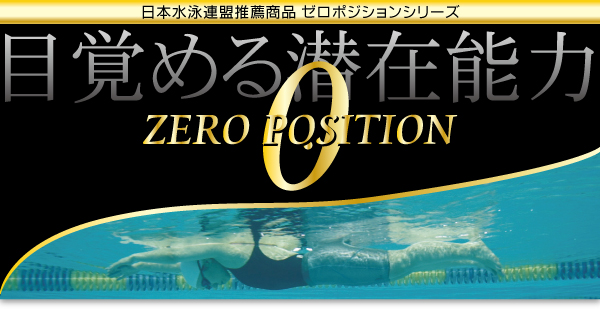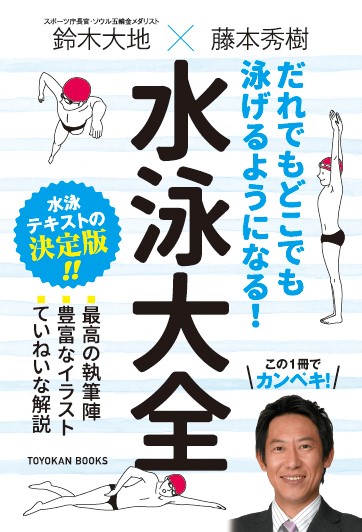泳ぎの質を、数字で見える化しませんか?
水泳が日課になっているあなたなら、ただ泳ぐだけでは満足できない日がきっとあるはずです。
もっと効率的に泳ぎたい。
自分の成長を数字で確かめたい。
そして何より、毎日の練習を“積み上げる喜び”に変えたい。
そんな想いを抱いたとき、スマートウォッチは最も心強い相棒になってくれます。
でも、いざ選ぼうとすると
「どれが本当に水泳に向いてるの?」
「SWOLFってなに?」
と、分からないことだらけ。
正直、この記事を書いている著者も、ランキングサイトなどを見ても、一般向けのランキングばかりで、スイマー向けの適切な説明が書かれたオススメ記事がありませんでした。
だからこそ、今回の記事では、実際に水泳を習慣にしている人・泳げる人に向けて、
「失敗しない水泳用スマートウォッチの選び方」
「本当におすすめできるモデル」
「購入後すぐできる活用法」
までを、丁寧に解説していきます。
プールでの距離計測やストロークの可視化はもちろん、オープンウォーターでのGPS活用や日常使いでの健康管理まで、実際の体験談を交えながら“リアルに使える情報”を厳選してお届けします。
スマートウォッチは、買った瞬間がゴールではありません。
あなたの泳ぎを支え、記録を見える化し、練習の質を上げるための“ツール”です。
本記事を通して、あなたにとって最適な1本を見つけ、自信と楽しさに満ちた水泳ライフを育てていきましょう。
先にランキング、そのあとに詳細説明を記載していきます。是非、詳細説明を読んで、ご自身にあったものを選んでみてくださいね!

オススメ商品ランキング|目的別に選べる注目モデル
スマートウォッチを水泳で活用したいと思っても、実際にどのモデルが自分に合っているのか迷ってしまう方は多いはずです。そこでこのセクションでは、泳ぎを日課にしている人やトレーニング目的で使いたい方に向けて、本当におすすめできるモデルを厳選してご紹介します。
初心者でも扱いやすいエントリーモデルから、トライアスロン対応の本格派まで、目的別に比較しやすいランキング形式でお届けしますので、ぜひスマートな1本選びの参考にしてください。
初心者向け:コスパ重視モデル(HUAWEI Band 10など)
「スマートウォッチを使ってみたいけれど、最初から高額なものに手を出すのは不安」
「自分が本当に使いこなせるかわからないし、まずはお試し感覚で始めたい」
そんなふうに考えている水泳経験者の方は少なくありません。
そこでおすすめなのが、1万円を切る価格〜2万円台で購入できる「コスパ重視モデル」です。代表的なモデルにはHUAWEI Band 10やCoros Pace 2があります。
これらのモデルは価格を抑えながらも、プールでの距離計測やストローク数のカウントといった基本的なスイム機能をしっかり搭載しており、初めてのスマートウォッチとしては非常に優秀です。
こだわりがなければ、トライアルとしては、HUAWEI Band 10がオススメです。
HUAWEI Band 10 スマートウォッチ 快適な付け心地 情緒モニタリング 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー ...
中級者向け:計測機能が充実したGarmin Venu 3S
「距離や時間だけでは物足りない」
「自分の泳ぎをしっかり分析して、もっと効率的に上達したい」
このように考える中級スイマーの方にとって、スマートウォッチは単なる記録ツールではなく、泳ぎを“進化”させるためのパートナーです。
ただ、モデルが増えてきた今、「どこまでの機能が自分に必要なのか」「高機能すぎても持て余さないか」が悩みの種となることも少なくありません。
その点でおすすめなのが、Garmin Swim 2とGarmin Venu 3Sです。
Garmin Swim 2はその名の通り“スイマーのために作られたモデル”でしたが、現在は発売停止されているので、Venu 3Sの方がオススメです。
Venu3sは「スイミング後の心拍推移が確認できて、オーバーワークに気づけた」「他のスポーツと組み合わせた総合的な健康管理に便利」と評価されています。
いずれも、日々の練習データをクラウド経由で保存でき、Garmin Connectを使ってトレンド分析や週単位での振り返りが行えるのも大きなメリットです。
GARMIN(ガーミン) Venu 3 Black / Slate AMOLEDディスプレイ搭載 美麗液晶スマートウォッチ 高性能GPS内蔵 ...
上級・トライアスロン向け:オープンウォーター対応&GPS精度重視モデル
「トライアスロンの練習に対応できるモデルを探している」
「海や湖など、オープンウォーターでのGPS精度を重視したい」
このようなニーズを持つ上級スイマーやトライアスリートにとって、スマートウォッチに求められる機能は格段に高くなります。
もはや“記録のため”ではなく、“競技力を上げるための戦略的ツール”としての役割が求められているのです。
しかし、実際に市販されているスマートウォッチの中には、「GPSが不安定で海では誤差が大きい」「心拍数が正確に取れない」「トレーニングモードの切り替えが面倒」など、ハードな使用に対応しきれないモデルも少なくありません。競技志向のトレーニングでは、そのような誤差や手間がストレスになり、時には記録や安全にまで影響するリスクもあります。
このレベルのユーザーに特におすすめしたいのは、fēnix 8 Sapphire AMOLED 、、Apple Watch Ultraなどのハイエンドモデルです。
これらのモデルは、オープンウォーターでのGPS精度が非常に高く、水面下でも安定した衛星受信が可能です。。さらにGarmin ForerunnerやFenixシリーズは、**マルチバンドGNSS(複数の衛星信号を組み合わせて補正する技術)**に対応しており、海や湖などの環境変化にも強いです。
iPhone ユーザーであれば、Apple Watch Ultraのセルラーモデル
Androidなどの方は、fēnix 8 Sapphire AMOLED シリーズがオススメです。
ガーミン(GARMIN) フラッグシップモデル fenix 8 Sapphire AMOLED 47mm Ti Carbon Gray DLC/Black マルチス...
水泳用スマートウォッチの選び方:外せない3つの基準

水泳用のスマートウォッチを選ぶとき、多くの人が
「どのモデルを買えば失敗しないのか」
「何を基準にすればいいのかわからない」
と感じています。
特に初めて購入を検討する方にとって、ネット上の比較記事やランキングを見ても、自分に本当に合った商品がどれなのか判断するのは難しいものです。
特に一般の人には良いけれどもスイマーにとって良いのかどうか、など不安ですよね。
失敗を防ぐには、購入前に自分の使用目的を明確にし、最低限チェックすべき“基準”を理解することが重要です。
多機能であることは魅力ですが、必ずしも自分に必要な機能とは限りません。
まずは
「防水性能」
「装着感」
「計測機能」
という3つの視点から、冷静に自分にとって必要なポイントを見極めることが、失敗しない選び方の第一歩となります。
この章では、水泳用スマートウォッチを選ぶ際に最も重要な3つの基準について、詳しく学ぶことができます。
防水性能(ATM/IP規格)の見極め方

水泳経験者の方がスマートウォッチを選ぶ際に最もよく直面する悩みのひとつが、「防水性能ってどこまで信じていいの?」という疑問です。
特にプールでの長時間トレーニングやインターバル練習を行う方、または屋外のオープンウォーターで泳ぐ方にとって、防水性は単なる「耐水」では不十分です。
ネットで「防水仕様」と書かれていても、実際に泳ぎながら使用できるモデルとそうでないものがあるため、注意が必要です。「5ATM」と書いてあったから買ってみたのに、泳いだら内部に水が入り故障した…という失敗も少なくありません。
防水の「等級表示」が何を意味しているのかをきちんと理解することが、水泳用のスマートウォッチ選びの第一歩です。
防水性能を見る際にチェックすべきなのは、「ATM」と「IP規格」のふたつです。
まず「ATM」とは、気圧に基づいた防水性能の指標で、1ATM=水深10m相当を意味します。
一般的な水泳トレーニングに使うなら5ATM(50m防水)以上が目安となりますが、インターバルトレーニングや長時間の水中使用を前提にするなら**10ATM(100m防水)**を推奨します。
一方、IP規格(例:IP68)は、防塵・防水性能を別々に数値で表す国際規格で、特に末尾の数字「8」が水深1m以上での長時間使用に耐えうることを示しています。ただし、IP68であっても製品によっては「水泳は不可」と明記されている場合もあるため、製品の使用条件の確認は必須です。
実際の使用シーンを考えると、例えばGarmin Swim 2やApple Watch Ultraなどは、公式に「スイミングに対応」と明記されており、プールでのトレーニングやオープンウォーターにも耐えられる設計がされているので、安い中華製を選ばずに、しっかりとしたものを選ぶのがオススメです。
バンド素材やフィット感:快適に泳ぐための工夫

水泳を習慣的に行っている人にとって、スマートウォッチのバンドが泳ぎのパフォーマンスや集中力に影響を与えることは意外と見落とされがちです。
「泳いでいるときにズレてしまう」
「肌が擦れて痛くなる」
など、見た目ではわかりにくい悩みが多くあります。
泳ぎに集中したいのに、時計のズレや違和感が気になってしまうとフォームが崩れたり、ペースが乱れたりすることもあるため、装着感は決して軽視できないポイントです。
特に、インターバルトレーニングや2km以上の長距離スイムを行う人にとっては、バンドの素材や留め具の安定性が快適性に直結します。
結論からお伝えすると、水泳用にスマートウォッチを選ぶ際は、「軽量かつ柔軟性のあるシリコン系バンド」を採用しているモデルを選ぶのが最もおすすめです。
シリコン素材は水を弾きやすく、濡れても肌に貼り付かない特性があるため、長時間泳いでも蒸れやかゆみを感じにくくなります。
たとえばGarminのSwim 2やVenuシリーズのバンドは、医療グレードのシリコンを採用しており、水中での装着感や耐久性に優れています。
また、Apple Watch Ultraでは、オーシャンバンドという特殊なデザインがあり、海水でもしっかりと固定されるように設計されています。
計測できる泳ぎの指標(ストローク・SWOLF・心拍など)

水泳を本格的に続けている方にとって、「泳いだ距離」や「タイム」だけでなく、より詳細なパフォーマンス指標を知ることは、練習の質を高めるために欠かせません。
しかし、いざスマートウォッチを購入しようと思っても、
「SWOLFって何?」
「自分の泳ぎをどうやって数値化すればいいの?」
「心拍数って水中で本当に測れるの?」
など、多くの疑問が出てくるのも事実です。
専門性のない市販のスマートウォッチの中には、「スイミング対応」と謳っていても、実際にはストロークのカウントや泳法の識別精度が低かったり、心拍数がうまく記録されないモデルも残念ながら存在します。
これではせっかくの練習も記録があいまいになってしまい、分析や振り返りに活かせません。
水泳用スマートウォッチの中で重要な3つの計測指標は、
①ストローク数
②SWOLF(スウォルフ)
③心拍数
ストローク数は、1ラップで腕を何回回したかをカウントする機能で、フォームの無駄を見つけるのに有効です。
SWOLFは「スイム(Swim)」+「ゴルフ(Golf)」の造語で、1ラップにかかった時間とストローク数の合計値。
つまり、泳ぎの効率性を示す指標で、SWOLFが小さいほどスムーズな泳ぎができていることを表します。
心拍数は、そのままですが、有酸素・無酸素領域の把握に直結し、トレーニング強度の管理に役立ちます。
具体的なモデルで言えば、Garmin Swim 2は泳法識別(クロール・平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライ)やターン判定の精度が非常に高く、SWOLFやストローク数も自動で記録してくれます。
また、GarminやPolarの一部モデルでは、水中でも比較的正確な心拍計測が可能で、リアルタイムでの負荷把握や後からのログ分析がしやすくなっています。
一方で、廉価モデルではストローク数が正確にカウントされない、もしくは心拍が水中では取得できないケースもあるため、購入時には必ず「計測できる指標の内容と精度」を確認しましょう。
モデル選びで押さえておきたい比較ポイント

水泳用スマートウォッチを選ぶとき、「スペック表は見ても、結局何を重視すればいいのか分からない」と感じる人は多いです。
特に、すでに泳ぐことに慣れている方にとっては、「自分の泳ぎに本当に必要な機能かどうか」を見極める目が必要になります。
価格だけで判断してしまうと、実際の使い心地やトレーニングへの活用度に差が出てしまい、せっかくの投資がもったいない結果になることもあります。
この章では、
「GPSの有無・精度」
「心拍や酸素濃度の計測の正確さ」
「バッテリーや日常使用での快適さ」
という3つの観点から、モデル選びのコツをお伝えします。
これらは特に、週に何度も泳ぐ方や、トレーニングを日課にしているスイマーにとって、満足度を左右する大切なポイントです。単なる記録だけでなく、日々の生活やモチベーション管理にも関わる要素として、しっかり比較していきましょう。
GPS搭載の有無とオープンウォーター性能
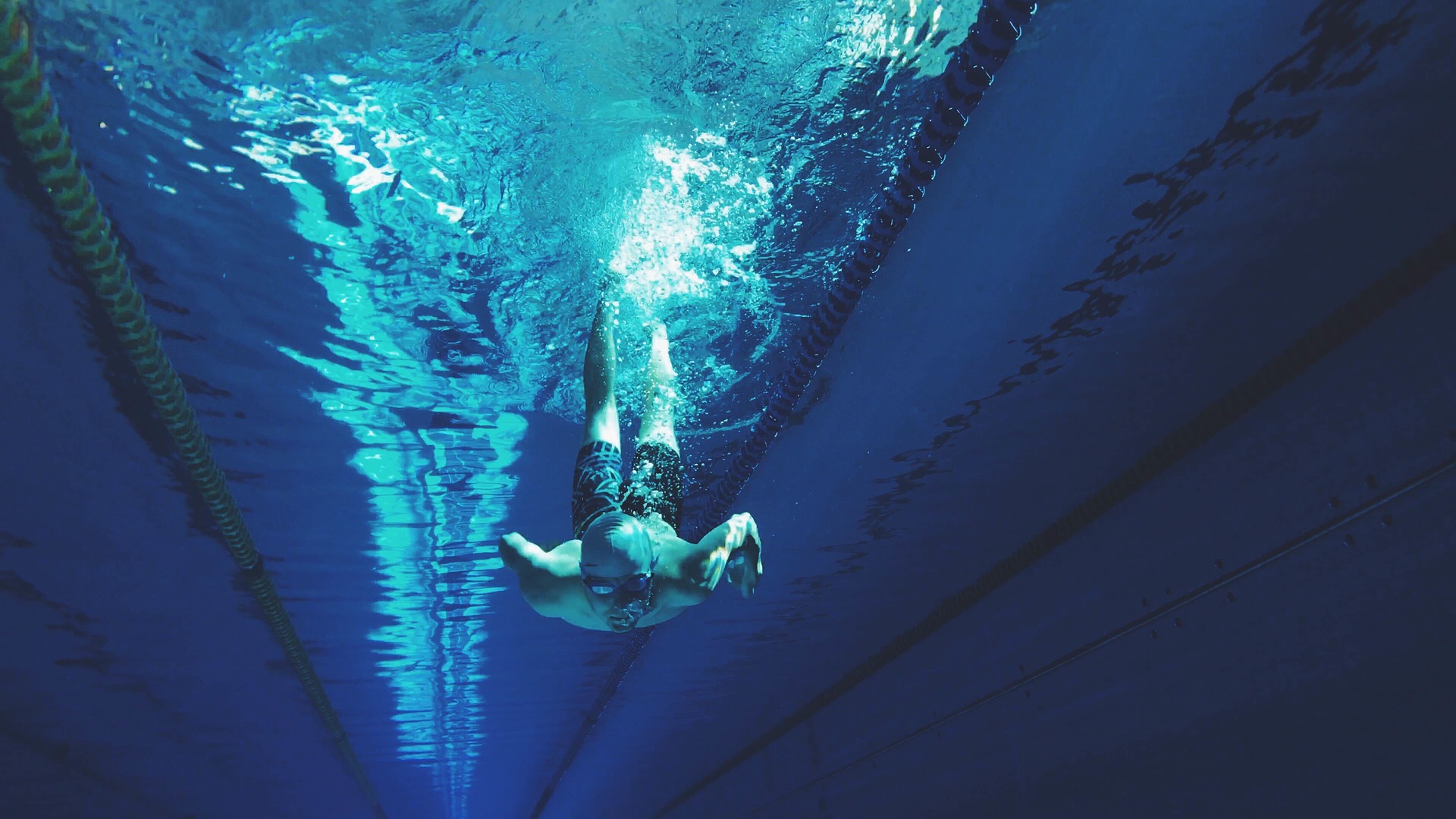
プールだけでなく、海や湖で泳ぐことがある方にとって、GPS機能は欠かせません。
しかし、すべてのスマートウォッチがオープンウォーターでの精度を担保しているわけではなく、「GPS付き」と書いてあっても水中では測位が不安定になるケースもあります。
また、価格帯によってはGPSの種類が旧型で、測位のタイムラグや誤差が大きいことも。これにより、正確な距離が測れず、練習内容の見直しやラップ管理がしにくくなることもあります。
結論として、オープンウォーターで使う場合は“マルチバンドGPS”もしくは“マルチGNSS”に対応したモデルを選ぶべきです。
たとえばGarmin Fenix 7やForerunner 955などは、複数の衛星信号を利用して測位誤差を最小化してくれます。
これにより、波がある状況や泳ぎの合間で手が水上に出るタイミングでも、高精度なログが残せます。
心拍数・酸素濃度・ストローク計測の精度
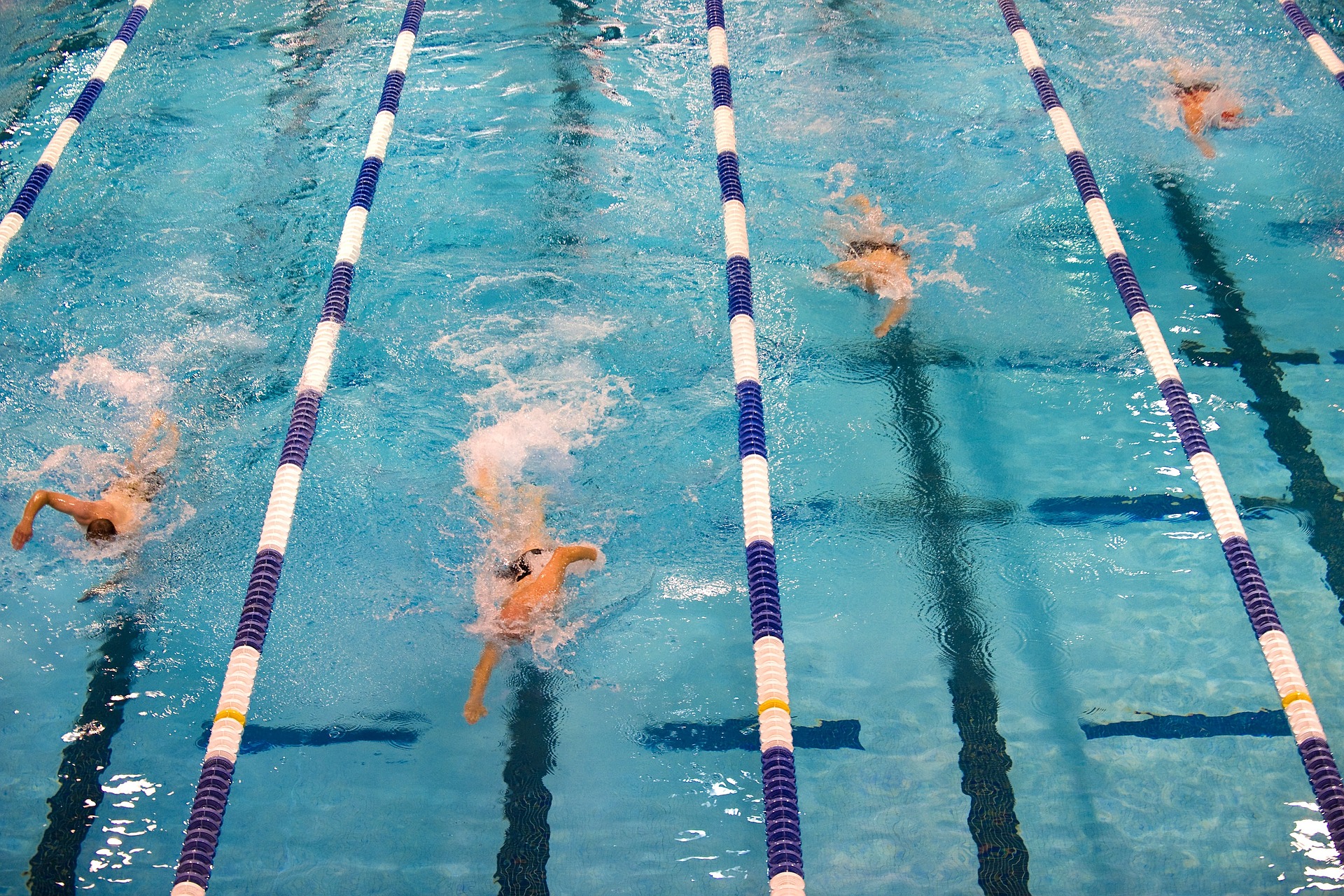
多くのスイマーが気になるのが「水中で心拍やストロークって正確に測れるの?」という点です。
心拍計測は水中では難しい技術であり、旧型のスマートウォッチでは精度が安定せず、表示されないこともありました。
また、泳法の識別やストロークのカウントが不正確だと、せっかくの練習記録も信頼性が下がってしまいます。
トレーニング強度を可視化したい人ほど、この精度は重要です。
結論から言えば、最新モデルであれば、水中でも安定した計測が可能になりつつあります。
Garmin Swim 2やPolar Vantage V2などは、光学式心拍計を搭載し、水中での使用にも対応しています。酸素飽和度(SpO2)を測る機能も一部モデルには搭載されており、高地トレーニングや長時間泳ぐ際の身体負荷を判断する目安になります。
たとえばGarmin Venu 3Sでは、スイム後に心拍グラフを振り返ることで、自分の心拍ゾーンの傾向を可視化でき、「中強度を意識した練習に切り替えた結果、疲労の残り方が減った」という体験談もあります。また、ストロークのカウントや泳法識別もかなりの精度で記録されるため、後からの振り返りに活かせます。
バッテリー持ち・画面表示・日常使いのしやすさ

いくら高性能でも、バッテリーがすぐ切れてしまうと、毎回の充電がストレスになって使わなくなるというのはよくある話です。
特にスイマーは「ジムで泳いで、帰宅後にログを確認する」ことが習慣になるため、1回の練習で電池残量が心配になるようでは安心して使えません。
また、画面が見づらい、操作が複雑という理由で、途中で使用をやめてしまう方もいます。
結論として、泳ぎを日常的に行う人にとっては、最低でも1週間以上バッテリーが持つモデル、屋内プールでも視認性が良いディスプレイを備えたモデルが理想です。
Garmin Fenix 7やCOROS Pace 3は、その点で評価が高く、最大2週間以上のバッテリー駆動が可能。
さらに、屋内プールのような照明の強い環境でも見やすい「トランスフレクティブ液晶」が搭載されており、トレーニング中に画面を確認するのも快適です。
たとえばApple Watchは高精細な画面が魅力ですが、使用頻度が高いと1日で充電が必要になるため、毎日のルーティンとの相性が問われます。
一方、GarminやCOROSはその点での安心感が高く、「週3回のスイム+日常の通知チェックでも余裕で使える」という声が多いです。
実際に使ったレビュー・体験談まとめ

どんなにスペックが魅力的でも、「実際の使用感」は数字だけでは伝わりにくいものです。水泳に慣れている方ほど、「ラップがちゃんと取れるか」「ターンで誤作動しないか」「プールでつけててストレスはないか」といったリアルな使用感や“ちょっとした違和感”に敏感です。
そうした感覚的な要素こそ、商品ページには書かれていない、貴重な判断材料になります。
この章では、実際にスマートウォッチを使用しているスイマーたちの声をもとに、使い勝手や誤作動、精度、注意点などをまとめていきます。
特に「プールでの泳法識別が合っているか」「海でのGPSログは信頼できるか」「バンドの肌触りはどうか」など、経験者ならではの視点で細かくレビューを紹介していきます。
事前にこうしたレビューを知っておくことで、「思っていたのと違った……」という購入後の後悔を減らすことができますし、自分の泳ぎ方に合ったモデルを選ぶヒントにもなります。
プールでの使い勝手と精度実測(ストローク・距離)

プールでの使用において最も気になるのは、「きちんとラップやストローク数が記録できるかどうか」です。
実際の声では、「25mプールでも正確に計測できた」「ターン判定が遅れてラップがズレることがあった」など、モデルによって精度に差があることがわかります。
特にインターバル練習やフォーム改善を目的とする場合、記録の正確性は非常に大切な要素です。
Garmin Swim 2を使っている中級スイマーのレビューでは、「クロールと平泳ぎの判定が正確で、ストローク数の推移を見ながらフォーム修正ができた」との声があります。
一方で、安価なフィットネストラッカーでは「泳法の自動判定がうまくいかず、全部フリースタイルで記録されてしまった」という例もあります。これはセンサーの精度やアルゴリズムの差によるもので、繰り返しの練習においては重要な差となります。
改善策としては、ラップ・泳法・ストロークがすべて正確に記録できるかどうかを、レビューやメーカーサイトで事前に確認することが大切です。
また、実際に使っている人の体験談を読むことで、自分の泳ぎ方との相性が見えてくることもあります。できれば購入前に、使用者のログをスクショなどで見てみると、よりイメージが掴みやすくなります。
海・湖などでのオープンウォーター使用感

オープンウォーターでは、GPSの安定性が記録の精度に直結します。
レビューでは
「Garmin Forerunner 955で1kmを泳いだとき、誤差が10m程度で驚いた」
「Apple Watch Ultraは波があってもスムーズに測位してくれた」
という声がある一方で
「腕を水中に入れている時間が長いとGPSがロストしやすかった」というケースもありました。
Garmin系の高機能モデルでは、手が水上に出た瞬間をとらえて衛星からの信号をキャッチする仕組みが組み込まれているため、ラップごとの軌跡が滑らかで、後から見ても非常に信頼性が高いです。
Apple Watch UltraもマルチバンドGPS搭載で、都市部や水辺でも精度のブレが少ないと評価されています。
ただし、スマートウォッチによっては「オープンウォーターモードがない」「そもそも泳ぐ用途では使えない」というモデルもあるため、購入時のスペック確認は必須です。
トラブル・注意点(プール側の規制や素材の傷)
実際に使用してみると、「思わぬところに落とし穴があった」というケースもあります。
よくあるのが、「プールによってはスマートウォッチの使用が禁止されている」といった事例です。
特に公共のスポーツ施設では、安全やマナーの観点から“装着禁止”となっていることもあるので注意が必要です。
レビューでは、「市営プールでは注意されて使えなかったが、ジムのプールでは問題なく使用できた」という具体的な声もあります。
まずは、使用前にプールの利用規約を確認しておくこと。
また、長く使いたい場合は使用後は真水での洗浄・乾燥を忘れず行い、トラブルを未然に防ぎましょう。
購入後すぐできる!効果的な使い方・トレーニング活用術

スマートウォッチを購入したあと、「結局、どう使いこなせばいいの?」と感じる方はとても多いです。
特に、機能が多いモデルほど最初は戸惑うことも多く、初期設定で止まってしまったり、時計としてしか使っていないというケースも見かけます。
本格的に泳ぎをしている方にとっては、毎日の練習を少しでも効率化したいと思って購入したはずなのに、活用できなければ宝の持ち腐れになってしまいます。
この章では、スマートウォッチを購入したその日からすぐに始められる活用法を3つのステップに分けて紹介します。
具体的には、アプリとの連携、練習メニューへの応用、日常生活での活用です。どれも特別な知識は必要ありませんが、少しの工夫と継続で大きな成果を生み出すものばかりです。
スマートウォッチは“測る道具”ではなく、“泳ぎを育てるパートナー”。この意識で使い始めれば、毎日のトレーニングがぐっと楽しくなります。
アプリ連携とデータ活用法(Garmin Connectなど)

スマートウォッチを最大限に活用するには、まずアプリとの連携が最重要です。
ウォッチ本体に記録されたデータは、基本的にスマホのアプリに転送して管理する仕組みになっており、ここを使いこなせるかどうかで“活用度”は大きく変わります。
「記録してるだけで振り返っていない」「グラフの見方がわからない」という状態では、せっかくのデータも意味を持ちません。
Garmin製品であれば「Garmin Connect」、COROS製品なら「COROS App」、Polarなら「Polar Flow」など、各メーカーが無料で提供している公式アプリを使います。
これらのアプリは、日々のスイムデータ(距離・ラップ・ストローク・SWOLF・心拍など)を時系列で表示してくれるだけでなく、週・月単位での平均や推移も可視化してくれます。
たとえばGarmin Connectでは、「先週よりSWOLFが改善している」「ストローク数が安定してきた」といった変化がグラフで見られるため、モチベーションの維持にも役立ちます。また、心拍数のゾーン別分析や、疲労度の把握も可能なため、オーバートレーニングの予防にも繋がります。
改善のポイントは、毎回の練習後に1〜2分だけでもアプリを開いてデータを見る習慣をつけることです。それだけで自分の泳ぎの傾向が見えてきて、「今日はキックに無駄が多かったな」「後半にペースが落ちてるな」といった分析ができるようになります。
アプリは“記録を見る場所”ではなく、“成長を感じる場所”として活用していきましょう。
自分に合った練習プランの作り方

「データを取るのはいいけど、じゃあそれをどう活かせばいいの?」というのは、多くのスイマーが感じる次の壁です。
ただ泳ぐだけではなく、記録をもとに自分専用の練習プランを作ることで、練習の質が大きく変わります。
たとえばSWOLFをもとに効率重視のフォーム改善を目指したり、心拍数の推移をもとに有酸素ゾーンをキープする持久力トレーニングを意識したりすることができます。
GarminやPolarなどの上位機種では、AIベースのトレーニング提案やリカバリーアドバイスもあり、「今日は軽めがいい」「この3日は高強度が続いてるから休もう」といった判断がしやすくなります。
一例として、週に3回泳ぐ方なら以下のような構成がおすすめです:
・1回目:フォーム意識の技術系(SWOLF重視、ゆっくり泳ぐ)
・2回目:中強度での持久系(心拍ゾーン2〜3維持)
・3回目:スプリントやインターバル(タイムと心拍ゾーン4)
改善策としては、自分のスケジュールと体調を考慮しながら、事前に「週のテーマ」を決めておくこと。
また、記録したデータをもとに、「次回はどこを意識するか」「今週はどう改善するか」を明確にしていくことで、ただのログが“伸びるための地図”に変わっていきます。スマートウォッチがあれば、それを根拠にした“自分専用の練習計画”が作れるのです。
普段使いで役立つ日常機能(通知・健康管理など)

スマートウォッチは「泳ぐときだけの道具」と思っていませんか? 実は、日常生活でもかなり便利に使える機能がたくさん詰まっています。水泳以外の時間にも活用することで、より持ち歩く意味が高まり、「トレーニングのための道具」から「毎日身につけたいパートナー」へと変わっていきます。
たとえば、スマートフォンとの連携によってLINEやメールの通知を受け取ることができるため、スマホをポケットに入れていなくても重要な連絡を見逃しません。
さらに、歩数・消費カロリー・睡眠の質・ストレスレベルなど、日常の健康管理まで記録してくれるモデルもあります。
特にGarminやFitbitなどは、水泳以外の健康指標も優れており、トレーニングと日常の体調管理を一体化できる点が特徴です。
レビューでも、「心拍数が日中ずっと高めだったので、知らずに疲れが溜まっていたことに気づいた」「睡眠スコアを確認するようになって、トレーニング強度と回復のバランスを取れるようになった」という声が多くあります。
改善策としては、最初から“トレーニング目的”だけでなく、“日常の体調チェック”としても活用する意識を持つことです。
スマートウォッチは単に泳ぎを記録する道具ではなく、自分自身の体調・パフォーマンスをトータルに支えるツール。
普段の生活でもしっかり活用すれば、より快適に、安心してトレーニングに向き合えるようになります。
まとめ

水泳に慣れているあなたにとって、スマートウォッチは「ただの記録ツール」ではなく、「泳ぎを支えるパートナー」です。
今回の記事では、水泳用スマートウォッチを選ぶときの基準、防水性能の見極め、用途別おすすめモデル、比較ポイント、実際の体験談、そして購入後の活用術までを、ステップごとに詳しく解説してきました。
特に覚えていただきたいのは、スイマーであれば、自分の泳ぎの目的やスタイルに合わせて“選ぶ視点”を持つことの大切さです。
ただ高機能なモデルを選ぶのではなく、「自分のトレーニングに本当に必要な機能は何か?」を考えることで、納得のいく買い物ができます。
そして、買った後の活用方法もまた重要。記録を振り返ったり、練習に活かしたり、日常生活でも使うことで、その価値はぐんと広がっていきます。
最初は操作に戸惑うこともあるかもしれません。でも、1週間、2週間と続けていくうちに、自分の泳ぎとデータが結びつき、スマートウォッチが“泳ぐ力を育ててくれる存在”に変わっていくはずです。
ぜひ、この記事を参考に、あなたにぴったりの1台を見つけてください。そして、その時計とともに、もっと楽しく、もっと深く、水泳ライフを充実させていきましょう。